「戦後80年」を考える関東私学中高生・教職員有志の会に参加しました。
この記事を寄せてくれた2年生の葛西純さん(生徒会会長)のコメントからご覧ください。
「今日は高橋哲哉さんをお招きして沖縄戦から学び、日本の戦争の歴史、今の社会情勢と言ったところから平和に結び付け、考えました。その後は感想交流を行い、zoomで全国の高校生が多く参加してくれていたので、山形、関東、福井の順でレポート発表も行いました。」高橋哲哉氏は哲学者・東京大学名誉教授。

<葛西純さんのスピーチ>
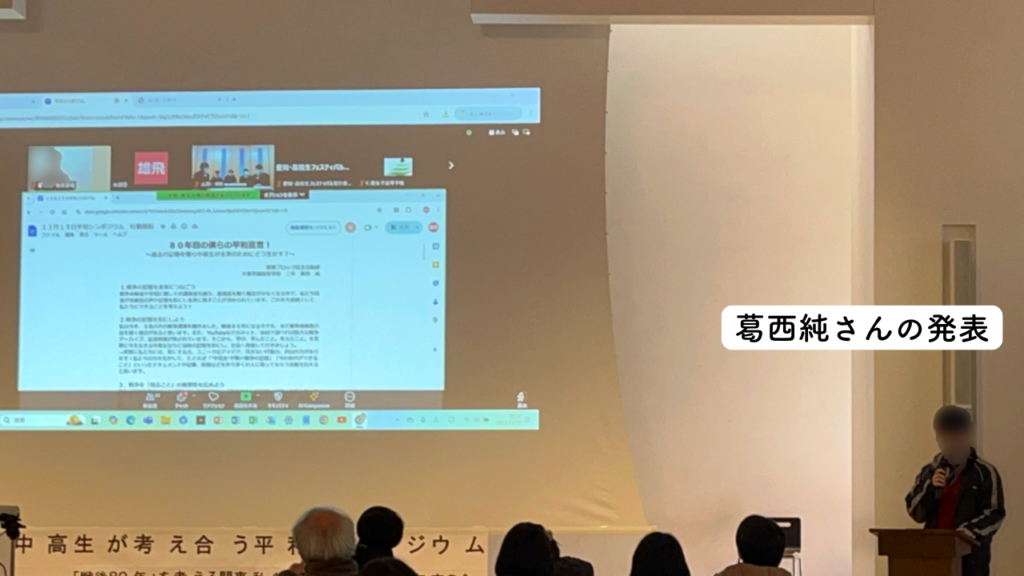
12月15日平和シンポジウム 行動提起
80年目の僕らの平和宣言!
~過去の記憶を僕ら中高生が未来のためにどう生かす?~
関東ブロック自主活動部
大東学園高等学校 二年 葛西 純
1.戦争の記憶を未来につなごう
戦争体験者や平和に関しての講演者も減り、直接話を聞く機会が少なくなる中で、私たち自身が体験者の声や記憶を形にし未来に残すことが求められています。これを大前提として、私たちにできることを考えよう!
2.戦争の記憶を形にしよう
私は今年、5名の方の戦争講演を聞きました。戦後80年になる今でも、まだ戦争体験者の話を聞く機会があると思います。また、YouTubeなどのネット、SNSで調べれば膨大な戦争アーカイブ、証言映像が残されています。そこから、学び、学んだこと。考えたこと。を実際に今を生きる中高生なりに当時の記憶を形にし、社会へ発信して行きましょう。→実際に私たちには、形にする力、ユニークなアイデア、尽きない行動力。沢山の力があります!私たちの力を生かして、たとえば「‘‘中高生‘‘が繋ぐ戦争の記憶」「今の世代ができること」といったドキュメントや記事、新聞などを作り多くの人に知ってもらう活動を行えると思います。
3.戦争を「知ること」の重要性を広めよう
戦争の歴史を知らない人が増えている現状では、「知ること」が平和への第一歩だと思います。そこで、多くの人が平和について知る、平和イベントを開催しよう。これは、既に取り組んでいる。または考えている人たちも多いかもしれません。私たちは、高校生交流やフェスティバルといったイベントを企画したり、参加したりするのが大好き!その勢いを戦後80年に生かせたら最高だと思う。戦争の被害、私たちが豊橋や、東京大空襲戦災資料センター、沢山のところで戦争、平和について学んだこと、他にも個人で行っている平和の取り組み、学校で行ている平和の取り組みなどを学べるイベントを企画し、少しでも多くの人に知ってもらえる場を提供しよう。戦争を知り、平和について考えることができる、資料を展示したり、発表会、講話を通じて誰もが学べる場を作ろう。中高生がイベントを企画することが大事だと思う。
4.平和に対して考えることを特別にしない
私たちの日常と平和を結びつけ、戦争や平和の問題を特別なことではなく、日常の問題として考えることが未来を作るために大切になると思います。
最後に・・・
私たちは、戦争の記憶を受け継ぐ最後の世代と言われています。だからこそ、平和の大切さを次の世代に繋ぐ責任があります。受け継がれてきたものを受け継ぐ責任がある。過去があるから今がある。戦争を知らない人が増えていく時代に、知らないままで終わらせないために、みんなで学び、伝え、行動を起こして行きましょう。私たちは恐らく、普通の人より戦争、平和について考える意欲や知識が多くあると考えます。私たちが学んできたこと、考えてきたことは間違いなく多くの人に響くと思います。既にこういった活動を行なっている人も多くいると思いますが、改めてまずは小さな行動から、それを周囲に広げていくことで、大きな変化生み出せると思います。過去を知って、今を知って私たちがどう行動するか、考えましょう。
高橋哲哉さんは若い人、中高生に責任はない、とおっしゃっていましたが、これからの日本を作っていく、有権者、主権者になる人としてどう行動するか考えることが私は大事だと思います。今日参加した皆さんに改めて平和に対して行動したい学びたいという意識に変化があればいいなと思い行動提起にしました。戦後80年そして未来のために中高生らしさを全面に生かし活動して行きましょう!!


このシンポジウムに参加した大東学園1年生の宮崎仁惇さんにもインタビューしました。
🎤 今回のシンポジウムに参加したきっかけや感想を聞かせてもらえますか。
「5月のゴールデンウィーク中、新入生歓迎で愛知県の高校に行ってきました。戦争のことや命の大切さを知り、その後、全私研で平和学習フィールドでさまざまなことを学びました。」
🎤 今回のシンポジウムで心に残ったことは何でしたか。
「2年生の葛西さんの発表、特に「最後に・・・」の部分の評価が高かったですね、それに高橋哲哉さんの『平和は守るものではなく、創り出すもの』という言葉が心に残っています。」